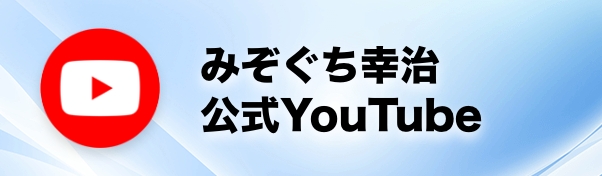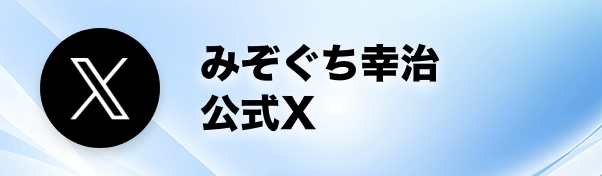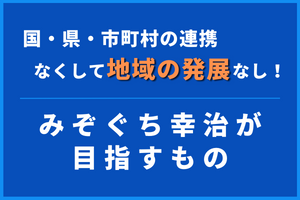日々雑感みぞぐち幸治のひとり言
川辺川ダム建設事業公聴会
2025年9月7日 (日) 07:38
 9月5日・6日に川辺川ダム建設事業公聴会が開催されました。
9月5日・6日に川辺川ダム建設事業公聴会が開催されました。
これは土地収用法に基づき、国土交通省がダムの事業認定を受けるために必要な手続きです。
このような会には反対を主張する方は積極的に参加されますが、賛成する方、容認される方はなかなか参加されませんので、住民を代表して応募させていただきこの機会を得たところです。
意見公述の途中、野次られたり、終わった後に怒鳴られたりしましたが、この場は意見の異なる方と議論する場ではないので話しかけていただいた方のご意見は真摯に聴かせていただきました。
これまでの経験上、私の発言がマスコミに切り取られて報道される可能性がありますので、ここに全文をアップします。
小学生や中学生、高校生等の子供達にも読んでいただけたら嬉しいです。以下参照
本日は川辺川ダム建設事業につきまして賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
私は1999年平成11年から人吉市議会議員、
2003年平成15年から熊本県議会議員として
長年、球磨川流域の治水対策の議論に関わってまいりました。
この間、計画の白紙撤回やダムによらない治水対策の検討、抜本的な対策がなされずに迎えた令和2年7月豪雨災害など、様々な経験をさせていただきました。
この中で学んだことの一つに「民意に従って政策を決定しても、地域住民の生命・身体・財産を守ることはできなかった」という事実です。
この事業を通して改めて「政治・行政の責任」「科学的根拠の大切さ」「後の世のためという観点」このことを分かりやすく地域住民に説明していくことの大切さを感じています。
そこで本日は「治水対策の目的と責務」「流水型ダムの意義と特徴」「科学的根拠と検証の成果」「代替案なしの現状」「事業を推進する上で大切なこと」この5つの観点から意見を申し上げます。
一つ目に(治水対策の目的と責務)です。
政治の要諦は地域住民の生命・身体・財産を守ることです。川辺川ダム建設計画が発表されるまでの洪水の歴史、古くは相良家古文書等からも球磨川流域は水害との歴史を積み重ねてきた地域だということが分かります。
私達は令和2年7月豪雨によりその脅威を目の当たりにしました。
県内の死者は67名、災害関連死は2名、負傷50名、住家被害は7,400棟を超え県内の被害総額は5,222億円に達します。
多くの人命を失われ、人々が傷つき、住み慣れた住宅や事業所を失い甚大な被害を受け、今なお元の姿には戻れない地域もあり深い傷跡を残しました。
被災後、地域の方々からは「治水対策はダムを含め、河川掘削、堤防嵩上げ等できる対策は全てやってほしい。二度と同じ悲劇を繰り繰り返さないようにしてほしい」という切実は願いが寄せられました。
そのことを思えば、国、県、流域市町村と連携して「流水型ダムを含めた緑の流域治水」を力強く推進していくことが政治や行政に課せられた責務です。
二つ目に(流水型ダムの意義と特徴)です。
今回、計画されている流水型ダムは、通常は河川の流れをそのまま下流に流し、洪水時のみ一時的に水を貯めて流量を調整する構造です。
この方式は川の環境や魚類の溯上に影響を与えにくく、清流や生態系を限りなく守る効果が期待されます。
実際につくばの土木研究所の超大型水理模型実験による増水時の川底の石の動き、平常時の川の流れを確認する実験やその動画を見ればよく理解できます。
従来、環境への悪影響を理由に反対意見も多くありましたが、是非、そのような皆様も含め多くの方々にご覧いただければご理解をいただけるのではないかと思います。
三つ目に(科学的根拠と検証の成果)
長年、この議論に関わったものとして重要なのは感情的な賛否ではなく、いかに科学的な検証を行い、その結果を住民に対して理解しやすい形にしていくのか、いわゆる「見える化」が重要だと感じます。
近年、熊本県では「緑の流域治水」という動画を作成し、球磨川の地形の特徴、洪水のメカニズム、緑の流域治水を分かりやすくまとめました。
それらを活用しながら小学校・中学校・高校と出前講座を実施しているところです。
国土交通省でも有識者の監修のもと、洪水時の水量、流速、土砂の動き等を詳細なデータに基づいて再現した映像が作成されています。
私も試聴しましたが、単なるCGではなく実際の地形データや過去の水害記録を反映し、科学的根拠に裏付けされ内容でした。
このような客観的資料は事業推進に向けての住民理解を深める上で極めて有用であります。
四つ目に(代替案ないの現状)です。
私は以前から川辺川ダム建設を中止、あるいは白紙撤回する場合、その方は責任を持って代替案を示すべきとの主張を行なってきました。
仮にその間に被害が出た場合、その責任もあるのではないか?
との趣旨の質問を当時の潮谷知事、蒲島知事、前原国土交通大臣にも行なったことがあります。いずれも明確な答弁はいただけませんでした。
しかしながら実際に災害が起こったわけです。私は国にも県にも大きな責任があっとと思います。もちろん私にも責任があると今でも思っています。
これまで示された代替案は遊水池の拡大や堤防強化などありましたが、豪雨災害の規模には対応できないものであります。
令和2年豪雨災害の規模を想定すれば、これらの代替案だけでは防ぐことが難しいと多くの専門家が指摘しています。
この現実を踏まえれば現時点では最も実効性の高い選択肢は、流水型ダムを含めた緑の流域治水であります。
五つ目に(事業推進をする上で大切なこと)以下の3点が大事だと考えます。
1点目は環境保全の徹底です。
流水型ダムは環境への影響を極力抑える構造ですが、工事の運用においても継続的な環境モニタリングを行い透明性のある情報公開を徹底することです。
2点目は地域の意見反映です。
流域住民が安心できるように説明会の開催、必要に応じて意見交換の場を設け、計画の進捗や安全性の評価を丁寧に共有すること。そして常に地域経済に貢献する事業であることを意識して行うことです。
3点目に流水型ダムを含めた緑の流域治水の実現です。
流水型ダムだけに依存するのではなく、環境に配慮した堤防強化、遊水池の整備、河川掘削、中小河川の整備、山林の整備、田んぼダム等、できることは全てやる必要があります。
これが地域住民の願いであり、次世代に地域づくりを託す上でも最も大切なことです。
私は豪雨災害発生後から市長と共に「我々は球磨川流域の治水対策とまちづくりを一体的に行う壮大なプロジェクトに挑んでいる」との認識を共有しています。
そのプロジェクトを前に進めるためにも流水型ダムを含めた緑の流域治水を実現して治水安全度を高めていくことが、安全安心なまちづくりには必要不可欠です。以上が私の意見であります。
最後に一言申し上げます。
令和2年7月豪雨災害では多くの人命を失われ、人々が傷つき、甚大な被害が出ました。
これまで球磨川流域の治水対策に取組んできたものとして責任の一端が私にもあると思っています。
だからこそ、私は豪雨災害後の2023年に行われた県議会議員選挙で「私の使命は流水型ダムを含め緑の流域治水を推進することである」と訴えて当選して今があります。
過去に熊本県は現在の民意はダム建設を望んでいないとの趣旨から川辺川ダム建設事業の白紙撤回を国に求め、事業が事実上ストップした経緯があります。
今は私が当選したこと、ダムを推進する知事、市町村長、国会議員が当選していることを思えば民意もまた「流水型ダムを含めた緑の流域治水を推進すべき」
あるいは「まちづくりの観点からも、次の世代が少しでも安心して暮らすためにもやむを得ない」との意思表示であります。このことを申し上げて意見公述といたします。
ご清聴ありがとうございました。